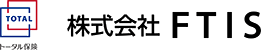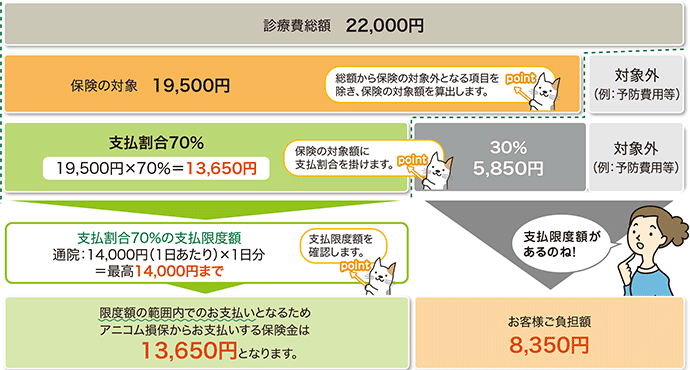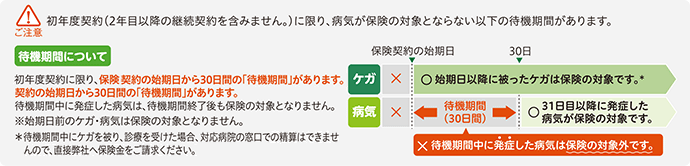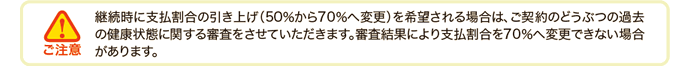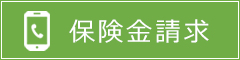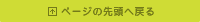- ペット保険に契約すると、どんなメリットがありますか?
- ずっと保険料は同じですか?
- 保険金の算出方法を教えてください。
- 保険始期日はいつになりますか?
- 補償はいつから始まりますか?
- 契約できるのは何歳までですか?
- どうぶつの正確な生年月日がわからない場合でも契約できますか?
- 健康でないと契約はできませんか?
- ワクチン接種をしていないと契約できませんか?
- 申込前に健康診断は必要ですか?
- 他のペット保険に契約していますが、契約できますか?
- 他のペット保険に契約していますが、どちらにも保険金請求ができますか?
- ペットが他人に身体障害や財産損壊を与えた時の損害賠償を補償できる特約はありますか?
- 以前契約していたことがありますが、また新規での申込みになりますか?
- どうぶつを譲渡することになりました。何か手続きが必要ですか?
- 契約した後に、途中で支払割合を変更できますか?
- 継続の手続きは毎回必要ですか?
- アニコム損保に直接請求をする場合、どんな書類が必要ですか?
- 「どうぶつ健保しにあ」で「どうぶつ健保ふぁみりぃ」に移行できる条件は何ですか?
ペット保険に契約すると、どんなメリットがありますか?
寿命の短いどうぶつにとっては、人間にとっての1年が4年にも匹敵するといわれています。
病院へ行くのが1日遅れると、どうぶつの症状はかなり悪化してしまうものです。
ペット保険を利用すれば、費用の高い高度医療を選択しやすくなり、治療法の選択肢も広がります。
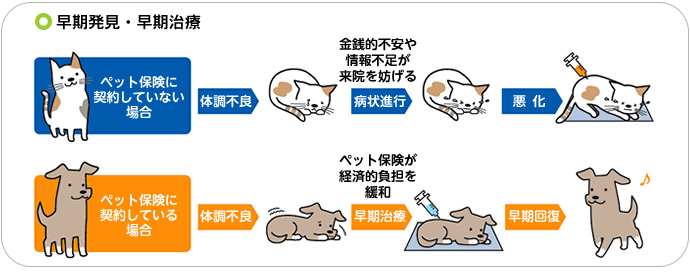
ずっと保険料は同じですか?
いいえ。どうぶつの年齢が1歳上がる度に、ご継続の時点で基本保険料は変更となります。(年齢は継続契約の開始日時点での満年齢です。)ただし、21歳以降は年齢にかかわらず20歳の基本保険料が適用されます。
保険始期日はいつになりますか?
お申込日の1ヶ月後(翌月の同じ日*)の0時が保険始期日となります。*31日などで同じ日がない場合は翌々月1日
※告知書の告知欄2および3において1つでも「ある」となる場合には、アニコム損保における引受審査が終了した日から1ヶ月後より保険責任が発生します。
契約できるのは何歳までですか?
新規ご契約の対象年齢は、「どうぶつ健保ふぁみりぃ」および「どうぶつ健保ぷち」は7歳11ヶ月まで、「どうぶつ健保しにあ」は8歳以上です。
- 新規ご契約の対象年齢であるか否かは、保険契約の始期日時点での満年齢で判断します。
- 新規ご契約の対象年齢は上記のとおりですが、原則ご継続は終身可能です。
どうぶつの正確な生年月日がわからない場合でも契約できますか?
どうぶつの生年月日は、血統書・ワクチン証明書あるいは診察券などでご確認ください。これらの書類をお持ちでない場合や記載のない場合は、かかりつけまたはお近くの動物病院で推定年齢を確認の上、ご記入ください。
- 生年月日の確認書類のご提出は不要です。ただし後日アニコム損保より血統書等の確認書類のご提出をお願いする場合や、動物病院に対しどうぶつの推定年齢を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
健康でないと契約はできませんか?
原則として、健康体であることが引受の条件です。
ご契約時(保険契約の始期日時点)に治療中、あるいは経過観察中のケガ・病気等がある場合、または治療が終了している場合であっても、ケガ・病気等の履歴によっては、お引受ができない場合や、「そのケガ・病気は保険金のお支払いの対象外」とする「特定傷病除外特約」をつけてお引受ができる場合もあります。一旦、お申込書類をアニコム損保にお送りいただいた後、担当部署にて個別に審査を行って決定します。審査結果の内容について開示することはできませんのでご了承ください。
なお、以下の病気に罹患している、または罹患している疑いがある場合には、契約のお引受自体いたしかねますのであらかじめご了承ください。
| (1)悪性腫瘍 (2)慢性腎臓病 (3)糖尿病 (4)肝硬変(肝線維症) (5)副腎皮質機能低下症(アジソン病) (6)副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群) (7)甲状腺疾患 (8)免疫介在性血小板減少症 (9)免疫介在性溶血性貧血 (10)巨大結腸症 (11)巨大食道症(食道拡張症) (12)膵外分泌不全 (13)猫伝染性腹膜炎(FIP) (14)猫白血病ウイルス感染症(FeLV) (15)バベシア症 (16)ヘモプラズマ症(ヘモバルトネラ症) |
ワクチン接種をしていないと契約できませんか?
ワクチン接種をしていなくても、契約は可能です。
ただし、接種しておらず、ワクチン等の予防接種により予防できる病気に罹患した場合は、保険の対象外となります。
例外として、獣医師の指示によりワクチン接種が受けられなかった場合この限りではありません。
申込前に健康診断は必要ですか?
不要です。ただしお客様には、ご契約のどうぶつの年齢や過去のケガ・病気等の履歴および現在の健康状態など、アニコム損保が告知を求めた告知事項について、お申込み時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
なお、告知事項が事実と異なる場合は、保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。
他のペット保険に契約していますが、契約できますか?
ご契約いただけます。必ず告知書の告知欄5に、他のペット保険等の契約内容をご記入ください。
なお、「どうぶつ健保ふぁみりぃ」と「どうぶつ健保しにあ」は重複してご契約できません。
他のペット保険に契約していますが、どちらにも保険金請求ができますか?
ご請求できます。
損害の額を超えてお支払いが発生した場合には保険会社間とご契約者等にて調整させていただくことがあります。
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」または「どうぶつ健保しにあ」と、「どうぶつ健保ぷち」の両方にご契約の場合、同一の入院・手術の診療費に対しては、「どうぶつ健保ふぁみりぃ」または「どうぶつ健保しにあ」と「どうぶつ健保ぷち」いずれか一方の保険契約からのお支払いとなります。
ペットが他人に身体障害や財産損壊を与えた時の損害賠償を補償できる特約はありますか?(「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保しにあ」のみ)
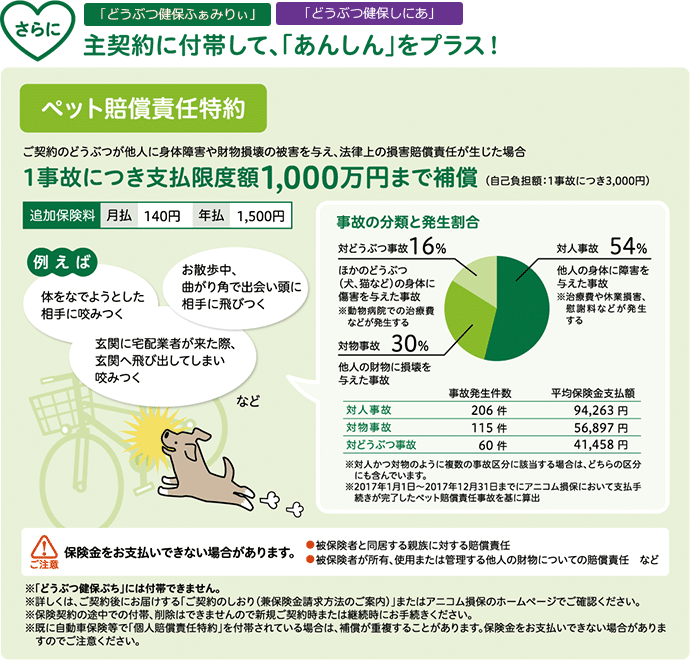
当社では、日本国内外での日常生活における賠償責任を補償する「富士通グループ団体保険制度 団体総合生活保険」個人賠償責任補償への加入をおすすめしております。
以前契約していたことがありますが、また新規での申込みになりますか?
一旦、この保険契約を解約された後に同じどうぶつについてお申込みいただく場合、新規契約の扱いとなるため、再度申込書や告知書等の提出が必要となります。なお、新規契約は、告知内容によりご契約のお引受ができない場合や、特定傷病除外特約が適用されることがあります。また、保険契約の始期日より前に被っていたケガおよび発症していた病気等、ならびに待機期間中に発症していた病気等については保険の対象外となりますので、以前の契約で対象となっていたケガ・病気が補償されないことがあります。
どうぶつを譲渡することになりました。何か手続きが必要ですか?
ご契約者本人よりアニコム損保あんしんサービスセンターまでご連絡ください。
ご契約の継続を希望される場合、されない場合に応じて手続方法(書類)をご案内します。
- 団体扱・集団扱特約が失効し、次年度は一般扱にてご継続となりますが、自動継続ではありませんので、ご継続いただく際には必ず「継続契約申込書」のご返送が必要です。
あんしんサービスセンター
- 電話番号:0800-888-8256
- 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
- 受付時間:平日 9:30〜17:30 / 土日・祝日 9:30〜15:30
- サービス向上のため、通話内容を録音させていただきます。
アニコム損保に直接請求をする場合、どんな書類が必要ですか?
アニコム損保に直接保険金を請求する際には、以下の書類が必要となります。
(1) 保険金請求書
(2) 診療明細書または領収書
(3) 手術内容証明書(未対応病院で手術を受ける場合)